
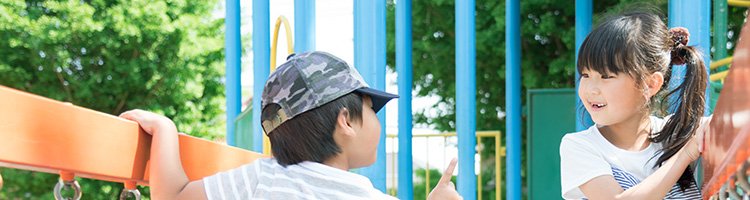


- トップページ
- SKJ対談
SKJ対談
みんなでこどもの命を守ることが
当たり前の社会になるために
Communication(通じ合う)とEducation(教育)の二つの意味を込めた「水ケーション」という活動を行う萩原 智子さん。元オリンピック日本代表として経験を活かし、こどもたちに水の大切さと楽しさ、そして怖さ。また、事故予防の知識をもつことはこどもの権利であり、生きる力を育むということについて話を進めます。さらに親子で一緒に体験活動をすることの大切さについて伝えていきたいと語ります。Safe Kids Japanとしてもこどもの水の事故予防には力を入れています。水辺での体験活動の素晴らしさと課題について、萩原さんの想いをお聞きしました。

こどもの水の事故は、なぜなくならないのか?
- 大野 美喜子
(以下、大野) - 毎年、ゴールデンウイークあたりから夏にかけて、こどもの水の事故が起こっています。辛く悲しい事故なのに繰り返されてしまうのは、徹底した事故の原因究明をする仕組みが整っていないことが、理由の一つではないかと私は思っています。原因究明されなければ、どうしたら予防できるのかも分からない。しかしこどもの水の事故の原因究明や予防を議論する仕組みが、残念ながら日本にはまだ整っているとは言えません。
- 萩原 智子
(以下、萩原) - こどもの水の事故件数は増えているのですか?
- 大野
-
こどもの水の事故は、実は10年前と比較すると減っているのです。事故予防の啓発活動が身を結んだこともありますが、少子化の影響でこどもの数そのものが減っていますから、単純に「こどもの水の事故件数が減った」とは評価しにくい面もあります。
例えば「水辺ではライフジャケットを着けよう」という意識は年々広まってきています。しかし、普段は使用しないライフジャケットをこどもが水辺に行くときのためだけに購入する、もしくは借りるというハードルを躊躇なく超えるまでには、保護者の理解が深まっているとは感じられません。こどもの成長に合わせてサイズも変わっていきますから、親の負担は大きいです。 - 萩原
- 確かに保護者としては悩ましいですね。でも毎年夏になるとこどもの水の事故が報道され、そのニュースを見るたびにやはり心が痛みます。
私は、事前の準備こそが大切だと思っています。水辺のどこにリスクがあるのか、事前にリサーチして知っておくことで防げる事故もあると思うのです。私の友人の話ですが、家族で初めてキャンプに行ったとき、事前に天候を調べてなかったので現地で大雨に降られてしまい、こどもは泣くは、結局ホテルに泊まることになるはで、散々だった!失敗した!と言ってました。せっかくの親子キャンプなのに、初めての体験が怖いものになってしまったら、こどもが自然体験から遠ざかってしまうかもしれない。もったいないですよね。
海や川だけではなく、学校のプールでも同様のことは言えます。深さや温度などはプールによって異なりますから、こどもの安全のために指導者は事前に調査・準備しておくことが必要です。

自然体験は事前準備が大切さだと語る萩原さん。
「水ケーション」で伝えていきたいこと
- 萩原
-
私が2015年から取り組んでいる「水ケーション」は、水とCommunication(通じ合い)、そしてEducation(教育)をかけて名付けた体験型のプログラムで、学校の授業や行政・企業と連携し、水の大切さや楽しさ、そして怖さを伝えています。2015年以降、計1400人以上のこどもと触れ合ってきました。
プログラムを実施する際、必ず行うのは事前リサーチです。実施場所のプールや川や沢の様子は必ず事前に調査します。学校でプログラムを実施するときは、参加するこどもたちの泳力についても必ず事前に教えてもらうようにしています。これらの情報をもとにプログラムを構成するので、内容は実施対象に合わせてすべて異なります。


萩原さんが森林セラピストの小野 なぎささんと一緒に行う「水ケーション」の様子。森の大切さや役割を座学で学んだ後に、萩原さんによるプールでの水泳教室や自然体験が行われる。(画像提供:萩原 智子)
- 大野
- それはすごいですね。これまで行ってきたプログラムの中で、特に印象深いものはありますか?
- 萩原
- そうですね...、例えば高知県土佐町で実施したプログラムではいろいろと考えさせられることがありました。小学校と自治体と連携して実施しましたが、そのときに先生や自治体の方が「自分たちがこどもの頃は川に飛び込んで泳いだもんだよ」と思い出を語っていたんです。当時のこどもは川で遊びながら楽しさも怖さも学んでいたんだと感じました。先輩や親から教えてもらったりして。でも、いつの間にか川はとても危険な場所になってしまって、大人もこどもも川に行かなくなってしまった。だから川の楽しさも怖さも情報共有されることがなくなってしまったと思うんです。自然から親が離れるとこどもも離れ、次の世代も自然から離れてしまう。地域の自然に目を向ける機会が少なくなると、郷土を誇りに思う気持ちが薄れてしまう気がします。「水ケーション」のプログラムを実施することで、全国のこどもたちに水の楽しさと怖さ、自然の豊かさを伝えていきたいんです。
- 大野
- 今の保護者は共働きも多く、みんな忙しいですよね。こどもに自然体験をさせたいと思っても知識もないし、時間もない。リスクも分からなければ、その解決方法もわからない。大きな問題です。ただ私は、すべて保護者の責任にするのは、やはり間違っていると思います。これは自然の中で起こる事故だけでなく、こどもの事故すべてに言えることですが、地域や社会としてこどもを守る仕組みが必要だと思うのです。セーフキッズジャパンとしてもこどもの事故予防に関する啓発活動には力を入れていますが、保護者や教育機関、当事者だけに向けた啓発では事故を防げないもどかしさを感じています。

保護者だけの責任問題にせず、社会全体でこどもの命を守る仕組みを作りたいと語る大野さん。
テクノロジーの活用で守るこどもの命
- 大野
-
セーフキッズジャパンが扱うこどもの事故の中でも、水の事故は取り組むべき優先度が高い事故の一つです。
水の事故に関して私たちは「ライフジャケットを着用しましょう」と推奨してきました。でも啓蒙活動だけでは、人はなかなか動かない。どこでも安価にライフジャケットを借りられるような社会の仕組みを作る必要があるのです。だって、海に入るつもりはなかったけど、海を見たら入りたくなったなんてこと、ありませんか? 水辺のリスクは分かっていて、ライフジャケットを着て水の中に入りたいと思っても、その場で借りることができない(レンタルステーションなどが少ない)という環境が問題なんです。
最近、海岸に設置したカメラからAIで危険な水の流れや溺れている人を検知してライフセーバーに伝えるという「海辺の見守りシステム」が、神奈川県鎌倉市の海で運用が始まりました。こういうテクノロジーを活用した取り組みが広がっていくと、社会は大きく変わっていくのかなと思っています。 - 萩原
- すごくいいですね。アプリをかざしたら危険な場所がわかる、なんていうのもいいかも。こどもの事故予防にテクノロジーの活用、大賛成です!
- 大野
- これは水の事故だけでなくこどもの事故全体に当てはまることなのですが、事故が起こらなかったという「成功体験」が事故予防の意識と乖離してしまう難しさがあります。「今回大丈夫だったから次も大丈夫」という思いは、心理的に強化されていきがちです。リスクに対する慣れもあるかもしれません。しかしこどもは日々成長しますから、昨日までできなかったことが今日できるようになった、ということもありますよね。成長すればリスクも変わります。こどもの成長に合わせたリスクをすべて保護者が把握することは難しいものです。これからはテクノロジーがこどもの事故予防に大きな助けとなってくれるでしょう。誰かの責任にするのではなく、社会全体でこどもの命を守る。そんな考え方とシステムが当たり前の世の中になって欲しいと思っています。

こどもには命を守られる権利がある
- 萩原
-
私はこどもと一緒に水辺に行くときは、必ずこどもにライフジャケットを着せるようにしています。どんなに浅い川でも、必ず着せます。そして川でおもちゃやサンダルなどが流れてしまったとしても「あなたの命を守るために絶対に追いかけないで、諦めて」と伝えています。こういう話は日頃からしておくといいですよね。なぜ追いかけてはいけないのか、諦めないといけないのか。そこにどんなリスクがあるのか理解できていないと、やっぱりこどもはおもちゃを追いかけてしまう。水辺に行く前に、こどもに伝えておくことが必要だと思います。
文科省の学習指導要項に着衣水泳の指導が記載されていますが、学校が指導するかどうかは任意です。でもそれではこどもの水の事故は無くならないと思います。こどもたちに着衣水泳の心得があれば、助かる命もあるはず。身体について学ぶ保健の授業はあるのに、命を守る授業が任意であることには疑問があります。こどもたちは日頃からもっと、事故を予防するための知識を得る機会があるといいと思います。 - 大野
-
まったく同感です。こどもたちには、命を守るための方法を知る権利があります。学校でも外部の専門家をもっと活用するなど、地域社会と連携していく仕組みがさらに整うといいですね。
予防って、要は「刷り込み」だと思うんです。海や川ではライフジャケットを着る。大人もこどもも、まだそういう思考になっていないのは、事故予防のための刷り込みができてないからではないでしょうか。 - 萩原
- 今、こどもには「生きる力」を身に付けさせるべきだと言われますよね。こどもが水辺の事故を予防する方法を知ることは、まさに「生きる力」が身に付いているということだと思います。

こどもたちが命を守ることについて学ぶ機会をもっと増やすべきだと萩原さん。
大人はこどもと一緒に体験を楽しんで
- 大野
- 私は田舎で育ちましたので、自然から学ぶことが多いことをよく知っています。自然に触れるとき、自分が生きていることを実感できるんです。雄大な自然の前では、日々の悩みなんかどうでも良くなるというか(笑)。それを実感できるのは、自然体験しかないですよね。
- 萩原
- こどもの感性に親が驚かされるのも自然体験ならではですね。こどもがまだ幼かったとき、公園の小高いところから落ち葉だまりに向かって滑って転がってきたことがありました。落ち葉だらけになった息子を見て私が笑ったら、こどももすごく嬉しそうに笑って「落ち葉って温かいんだね」と私に言ったんです。落ち葉が温かいなんて、大人では思いも付きません。こどもの感性に驚かされました。そのあと「ママも一緒に滑ろう」と言われて大変でしたけど(笑)。
- 大野
- 素敵なエピソードですね。こどもの頃に五感を使う経験を多くすることは、生きていく上でとても大事なことなんじゃないかと思います。お母さんが一緒に滑ってくれたのも、息子さんとしては嬉しかったんじゃないですか?
- 萩原
- それはあるかもしれません。実は大人がこどもと一緒に何かを体験することは、とても重要なことなのではと思っています。元バレーボール選手の益子直美さんが主催しているイベントをお手伝いしたことがありますが、親や指導者も一緒に参加したことがありました。そうしたらこどもたちがものすごく喜んで、「あんなに楽しそうな先生、初めて見た」とか、「大笑いしているお父さんを見たのは初めて」とか。そのときに、大人とこどもが一緒に何かを体験することはとても大切な時間なんだと実感しました。それからはそんな機会をもっと作りたいと思い、活動しています。
- 大野
- スポーツでも自然体験でも、大人がこどもと一緒に体験することが大切なんでしょうね。ただし大人は事前にリスクを把握しておく必要はあります。その上で、思いっきりこどもと一緒に楽しんで欲しいものです。

体験は親も一緒にこどもと楽しむことが大切だと語る萩原さんと大野さん。
こどもの事故予防のために、今後取り組みたいこと
- 萩原
- 「水ケーション」の今後としては、学校などの教育機関との連携をもっと深め、水の大切さ、水の楽しさと怖さをより一層伝えていきたい。大野先生が言う通り、まさに刷り込みですね。こどもたちに「生きる力」を身につけてもらえるようにプログラムを進化させていきたいです。そして保護者にも参加してもらえるような工夫も考えたいですね。親子一緒に水の循環や大切さ、水の楽しさと怖さを体験してもらえば、自然への向き合い方も変わってくるのではないかと思います。
- 大野
- 保護者とこどもが一緒に体験できるプログラムって、いいですね。セーフキッズジャパンとしては啓発活動を継続して行うと同時に、今後は新しい社会の仕組みづくりにも注力していきたいと思っています。こどもの安全を保護者や教育機関だけの責任にせず、社会全体で考えるようにしていきたい。そのためにはメディアへの働きかけも重要だと思っています。アメリカではこどもの安全に沿った番組制作が行われています。CMでも、安全面に配慮していない表現であれば視聴者からクレームが来ます。そうなれば、企業は社会的制裁を受けることになります。つまりそれだけ社会の中に、こどもの安全・事故予防への意識が浸透しているのです。日本はこの点では、まだ遅れています。やっと最近、「自転車に乗るときはヘルメットをする」ことがメディアの表現の中で当たり前になってきましたが、ベビーベッドの中には物を置かない(窒息を防ぐ)とか水辺のレジャーではライフジャケットを着けるとか、もっと徹底して欲しいと思っています。メディアでの表現が徹底されれば、自然と社会の常識になっていくでしょう。セーフキッズジャパンとしては、そんな働きかけもしていきたいと思っています。
- 萩原
- こどもの安全を守る社会は、人と人とのつながりが根底にあると思っています。自分だけが良ければいいのではなく、みんなが幸せになれることを考えられる社会になるといいですね。みんなの幸せを考えることは、いつかそれが自分の幸せにつながっていくと思っています。
- 大野
- 私もそう思います。社会が自分ごととしてこどもの安全を考えるようになって欲しい。そのためにも、まだまだやらなくてはいけないことがいっぱい! こどもの事故を少しでも減らすために頑張ります!
- 萩原 智子
- 元オリンピック女子競泳日本代表。現在はスポーツアドバイザーとしてスポーツ団体等の役員を務めながら、メディア出演や講演活動等も行っている。山梨県・福島県・愛知県春日井市で萩原 智子杯水泳大会を開催。水泳の普及活動をはじめ、水の大切さと感謝の思いを伝える「水ケーション」の活動にも注力している。一児の母。
- 大野 美喜子
- Safe Kids Japan理事長。国立研究開発法人 産業技術総合研究所人工知能研究センター 主任研究員。AIを用いた傷害予防教育プログラムの研究などに携わる。二児の母。
取材編集:帆足 泰子
撮影:西川 節子
撮影:西川 節子


